|
Name: KRY
Date: 2009/03/23(月) 01:44
No:2328
|
削除 |
|
Title: 手元供養
|
 |
はじめまして。
私の実家のことなのですが、神道なのですが、こちらで何か助言を頂ければと
相談させていただきます。
先日、弟が、生後4ヶ月の娘を遺して27歳の若さで亡くなりました。
急なことでしたので、両親もお嫁さんも気丈に振る舞ってはおりますが、
弔問客が少なくなり、おおきな遺骨をお墓におさめたあと、
悲しみや寂しさが押し寄せてくるのではないかと思っています。
(私がまだ心が麻痺しているようなので、ほかの家族もそうなのではと・・・)
そこで、遺骨ペンダントというものをインターネットで知ったのです。
弟がお墓に入ったあとでも、いつでもずっとそばにいてくれたら、
両親もお嫁さんも少しは癒されるのではないかと。
話してみて、もしみんなが望むのなら、家族のぶんを購入しようかと
思っています。
ただ、本来お墓にいれるべきものを、少しづつ取って、家族それぞれが
持っているということが、いいことなのかがわかりません。
それによって弟が成仏できなかったり、あの世でつま先が少し欠けてる、
などということになりはしないでしょうか。
販売サイトは山ほどあり、どのサイトにも「手元供養は悪いことではない」
と書いてあるのですが、先方はご商売ですからそう仰るだろう、と
穿った見方をしてしまいます。
畑違いの相談で恐縮ですが、私の実家はたまたま先祖が神道にしたという
だけで、とくに宗教にこだわりはありません。
(こういう言い方は宗教家の皆様に失礼でしょうか、すみません)
ただ、弟のこれからの魂が安らかであり、遺された私の家族の気持ちが
少しでも楽になれば、そして弟とともに前に向かうことができれば、
どの宗教のしきたりで弔っても構わないのです。
失礼な質問の仕方かもしれません。申し訳ございませんが、ご回答を頂ければ
幸いです。
よろしくお願い致します。
|
|
|
|
|
|
Name: 浄徳寺隆胤 [URL]
Date: 2009/03/23(月) 07:38
No:2330
|
削除 |
|
Title: Re:手元供養
|
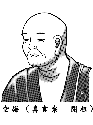 |
これは僧侶や神職の各人の考え方により答えは違ってくるものと思います。よってここでの意見を参考になされてお考えになってください。
他の僧侶の方々のご意見もお聞かせいただきたくお願い申します。
お亡くなりになられた故人は遺された家族のことを思います。
遺された家族も早く立ち直る方もおられれば、何年も引きずってしまう方もおられるのも確かです。お墓に納め、土にかえしてあげるのが本来の姿です。しかし、立ち直れないということになれば、しばらく遺骨の一部を頂いて、手元に置くというのも、遺された家族が立ち直れる手段であれば、それもよいのではないかというのが私の考えです。本来は土にかえさなければならないのですから、立ち直るめどがつきましたら、本来の場所に必ず納めてください。
以上80を越える老いぼれ僧侶の考えです。
陽明山浄徳寺
山主 近衞隆胤
合掌
|
|
|
|
|
|
|
Name: 天台沙門
Date: 2009/03/23(月) 08:55
No:2331
|
削除 |
|
Title: Re:手元供養
|
 |
まずはお悔やみ申し上げます。
「若くして死ぬ」や「事故で死ぬ」ということを、宗教学や民俗学では「横死=異常死」といいます。日本では、古来から異常死をした死者は手厚く弔うべきとされてきました。古代的感情では、そうしないと「祟る」のですが、現代的理性では「受け容れがたい突発的な死」というわけです。手厚く弔わなければ、生きている人間はその「死」を受け容れたり乗り超えたりできないのですね。
宗教儀礼というものは意外と合理的なものです。
>>本来お墓にいれるべきものを、少しづつ取って、家族それぞれが持っているということ
>
いわゆる「分骨」という作法です。仏教的には、釈尊ご自身の葬儀に際し「火葬」と「分骨」がなされておりますので、問題ない方法と考えます。「骨は一緒にしておかねばならない」という意識は、人類に普遍の「骨が欠けていると(この世またはあの世に)再生できない」という感情に根ざすものでしょう。
死者が「千の風」になったり「草葉の陰」から見守ってくれるという感覚、つまり死者を身近に感じるために、分骨した遺骨を身につけているという方法は形見の品を愛用する気分と一緒ではないでしょうか。
宗教者が分骨や手元供養をおおっぴらに勧めないのも、業者さんが手元供養の正当性を主張できないのも、遺骨が分散すると生まれ変わりに差し支えが出るという原始的感情を捨てきれないからです。 (註:業者主導の「手元供養」は、死者は死者の場に祀り籠めておかないといけないという民俗的宗教意識を、どうしても乗り超えられない。)
>>弟のこれからの魂が安らかであり、遺された私の家族の気持ちが少しでも楽になれば、そして弟とともに前に向かうことができれば、どの宗教のしきたりで弔っても構わないのです。
>
まったくもって、そのとおりだと考えます。
葬祭儀礼というものは、死者のためにやっているようですが、実際は生者のために行っているものです。人がよく知っている人の死に遭ってしまった時に感じる、悲しい・辛い・寂しいといった気持ちをなんとかしていくため、人類は葬祭儀礼というものをそれぞれの文化のなかで経験的に作り上げてきました。だいたい、死者の鎮魂と生者の鎮魂とを分けて考えること自体、不自然でしょう。
死との邂逅やら不治の病の宣告やらを、心理学的には「喪失体験」というそうですが、これの回復には「共通の体験をした人々(および共感者)との連帯」と「絶対的な時間の経過」が必要だそうです。
葬祭儀式に参加するということは、参加者が互いに「悲しいのは自分だけではない」と感じることで、より悲しい人を支えてあげようとか、自分の人生をきっちり生きていこうという気分になることです。これは「共感者との連帯」ということですね。
また、五十日祭・一年祭・二年祭(ですか?)などの定期的な祭祀は「時間の経過」に折り目をつけるということです。いわゆる通夜・葬儀だけで、喪失体験からの回復ができるはずもなく、まる2年くらいかけて故人のいらっしゃらない娑婆世界にゆっくりと「慣れて」いくしかないと考えます。
|
|
|
|
|
|
|
Name: KRY
Date: 2009/03/24(火) 21:29
No:2335
|
削除 |
|
Title: Re:手元供養
|
 |
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、本来は土に還すべきなんですね。
できれば、姪が大きくなるまでとか、両親が弟のもとに行くまでずっと私たち家族のそばにいてくれればと思ったのですが、そういうわけにもいかないようですね。
遺骨は弟そのものではない。遺骨を土に還しても、手元に持っていても、「弟が見ていてくれる」と思うことはできる。
頭ではそう思うのですが、今は寂しいから、弟が少しでもそばにいてくれるという選択肢にすがってしまうのだと思います。
もうすぐ50日祭なのですが、母がお墓をきれいに作り直してから納骨したいというので、遺骨はお盆の頃まで実家に置く予定でいます。少し時間があるので、それまでみんなの気持ちを見て、どうしても諦められないようなら、
「気持ちが落ち着くまで、指先くらい借りようか」
と言ってみようかと思います。
浄徳寺隆胤様
80歳を過ぎていらっしゃるとは、心強い限りです。
私は30近くなって初めて家族を亡くしたので、こういうことに関しては儀式のいろはも自分の感情も家族のこれからもわからないことだらけですが、私の何倍も、生死を見て儀式を行って来た大先輩にお話を頂けるとは。
どうもありがとうございます。
天台沙門様
>>弟のこれからの魂が安らかであり、遺された私の家族の気持ちが少しでも楽になれば、そして弟とともに前に向かうことができれば、どの宗教のしきたりで弔っても構わないのです。
>まったくもって、そのとおりだと考えます。
書き込んだあとに、やはり失礼だったと思ったのですが、そう仰っていただけると有り難いです。
仏様でもイエス様でも神様でも、そちらに行ってしまった私の弟をどうかどうかよろしくお願いします、という気持ちです。こういう罰当たりかもしれない気持ちを、僧侶の方が肯定して下さると少し楽になります。
どうもありがとうございます。
ところで、甘えついでにもう一つお伺いしてよろしいでしょうか。
分骨の際、儀式などはあるのでしょうか。
「ごめんね、もう少し一緒にいてね」
と言って、合掌するくらいで骨箱からかけらを取り出してしまっていいものか、それともきちんと宮司様にお願いしなくてはいけないのか。
いろいろとおすがりして申し訳ありません。
少しの間なら弟に甘えてしまっても駄目というわけではない、ということでお二方で共通して仰っているようですので、少し安心です。
人の死に接して生きておられる複数の方のご意見を頂戴できて心強いです。
よろしくお願い致します。
|
|
|
|
|
|
|
Name: 天台沙門
Date: 2009/03/26(木) 17:55
No:2338
|
削除 |
|
Title: Re:手元供養
|
 |
>>分骨の際、儀式などはあるのでしょうか。
>
私はとりたてての儀式は行っておりませんが、集骨時の儀式を援用する形で行います。それなりの形式を整えて、分骨の法要をなさる方がいらっしゃる可能性は大いにあるでしょう。
>>きちんと宮司様にお願いしなくてはいけないのか。
>
神道さんが分骨や遺骨の一部を埋葬しないということについて、どういった宗教的解釈をなさるのかが不明ですので、祭礼を司っていただく神職さんに事の是非をうかがっておかれるのが一番でしょう。
|
|
|
|
|
|